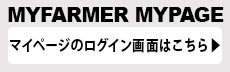農天気代表 小野淳さんの『農』天気ブログ
ある中学生の問いかけ
~オリンピック選手村で日本の農産物を食べてもらうためにGAPなどの認証をとるべきなのか?」について考えてみた 第1回~

※この季節 畑でとった野菜をそのままサラダにして食べることが多いです
毎週、芋煮会を開催している小野です。
簡単手軽に秋の野菜を堪能できて、しかも美味しい。(料理上手じゃなくてもまず失敗しない)「芋煮最強!」という確信を強めております。
さて、そんな最中ある中学3年生が畑を訪ねてきました。
そして表題の通りの難しげな質問を投げかけてきたのです。
彼の中学は私立で中高一貫なのですが、高校に上がる前に「卒業論文」が課題としてあるらしく、
そのなかでテーマとして選んだのが『東京五輪から考える農作物の持続可能性』。
今時何でもネットで調べられる時代ですが、基本対面での聞き取り調査などをしたうえでの執筆が義務付けられているとのことです。
なので突然現れたわけではなく、NewsPicksというニュースコメントサイトで私の発言を目にしてより詳しく話を聞きたいと丁寧な取材依頼メールをいただいていたのでした。
▼そのNewsPicksにおける私のコメントというのはこちら▼
東京五輪で日本の食材使えない?! GAP問題とは何か
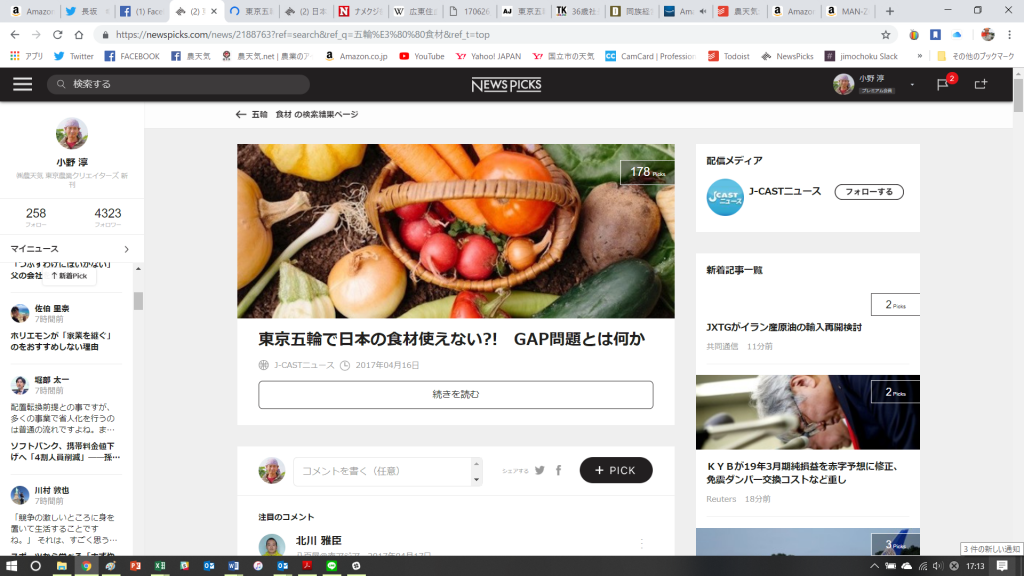
振り返ると結構強めなコメントしていますね(苦笑)。
主たる主張はここに書いた通りなんですが、
さすがにわざわざ聞き取りに来ていただき、さらにGAPを推進している某大企業の農業生産部門にも聞き取り済みということで、あらためてなるべく丁寧に説明してみようと試みました。なにせ中学3年生が農業に関心をもって現場リサーチしているっていうこと自体が感動的ではないですか!
彼の問いかけは大まかに3点
➀ 東京五輪を契機としたGAPなどの第三者認証取得推奨をどう思うか?
② 日本の農産物輸出の可能性をどうみるか?
③ 持続可能な発展(SDG‘s)というキーワードは何を意味するのか?
鋭く的確ですね。本当に14歳なんでしょうか?
③は私がテレビ番組制作から農業に転職した理由でもあるので、話せば長いことになってしまうので割愛しますが、①,②について私の見解をちょっとまとめてみます。
➀ 東京五輪を契機としたGAPなどの第三者認証取得推奨をどう思うか?
そもそもGAP(農業生産工程管理Good Agricultual Practice)って何?
というのは先の記事リンクを読んでみてください。
日本における第3者認証の代表格は有機JAS認定でしょう。あと最近は農産物というよりも食品衛生管理という面でHACCP(ハサップ)というのも話題になってきています。
私はかつて農業生産法人に勤めていたときにすべての出荷物において有機JAS認証をとるという方針でしたので、一通りの手続きや現場での管理、研修を通しての資格取得などを体験しました。
要は第3者認証というのは「流通する食品の適正な管理を資格を持った現場監督と認証機関が保証します」ということです。八百屋さんでただ大根が置いてあっても誰ががどのように栽培したものかわからない。安心して口にできるように公的機関がチェックすべし。ということですね。それだけ聞けば確かにその通り!と誰もが思うところだと思います。
しかし現状、日本の農産物では第3者認証はほとんど浸透していません。
大手スーパーなどではずいぶんと普及してきた有機JASですら全体流通量の0.3%です。
一体なぜでしょうか?

※この認証を受けなければ商品名に「有機」「オーガニック」などの表示は違法となる
これも端的に言えば「認証をとるコスト、日常的な記録業務などの煩雑さと手間に見合った高単価を付けたら結局買ってもらえない」というところに尽きると思います。
これは現場を体験した私は身を染みて感じるところです。
結局、日本の消費者の多くはそこまで気にしていないし、国産に対して安心感を抱いているので、第3者認証というなんだかよくわからないマークがついていても高ければ買わない人が多いということです。
その結果、有機JASに関しては、栽培方法は完全無化学肥料、無農薬でも認証はとらないという生産者はけっこういます。
例えば、最近人気の農産物直売所。
道の駅やJA系の大直売所が各地にでき、年商1億を超えているところも少なくありません。
ご当地感もさることながら圧倒的な強みは「鮮度と安さ」でしょう。
そこで求められているのは第3者機関による認証などではなく「気軽においしい」ということと消費者が抱きがちな「農家が直接売っているものは安心」という信頼感です。
そのマーケットが十分にあるにもかかわらず、認証をとることにコストをかけるメリットを感じる農家が少ないのは当然です。

※生産者と消費者の距離がもともと近いというのが日本の小規模農業の強み
そもそも認証は「信頼感がないからこそ必要とされる」ものだからです。
日本における個人の小規模農家と消費者にはすでになんとなくの信頼感が醸成されているために、認証はあまり必要とされていないのです。
反対に、大きな法人であったり大規模流通においては一定の需要があると言えます。
と、ここまで書いてすでにいつもの倍ぐらいの分量になってしまいましたので
続きは来週!
「日本国内流通では生産者と消費者の間に一定の信頼感があるために認証はあまり求められていない。しかし、ならば日本の農産物は国際的に流通させていく必要はないのか?」
ということについて次回,私見を述べます。
しかし、こんな本質的な話を引き出しかつ受け止める14歳すごすぎです!
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
新刊本「東京農業クリエイターズ」(イカロス出版)好評発売中!
http://hatakenbo.org/infomation/20180518_tokyonogyocreators
文・写真 小野淳
㈱農天気 代表取締役 農夫
NPO法人 くにたち農園の会 理事長
東京・国立市を拠点に幅広く農体験を提供
「都市農業必携ガイド」(農文協)
監修・実演「菜園ライフ~本当によくわかる野菜づくり」(NHKエンタープライズ)